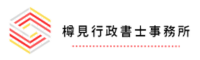こんにちは。行政書士の樽見です。
本日は古物営業における取引義務について解説します。
古物商が古物の取引を行う際、帳簿(台帳とも言ったりします)への記載、又は電磁的方法による記録の義務が定められています。これを「記録義務」と言います。
具体的には古物営業法第16条から18条に書かれています。
どんな時に、何を書いたらいいのか?
古物商は、
①古物の売買
②古物の交換
③古物の売買又は交換の委託
により、古物を受取り又は引き渡したときは、都度以下の方法で記録をしなければなりません。
1 帳簿(台帳)への記載
2 国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類への記載
3 電磁的方法による記録
記録事項については次の通りです。
①取引の年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴
④古物を受取り、又は引き渡した相手方の住所、氏名、職業及び年齢
⑤古物営業法第15条第1項の規定により相手方の確認のためにとった措置の区分
※特に非対面取引で相手方の確認をした場合には、身分証明書のコピーや画像も一緒に記録・保存しなければなりません。
また古物営業法第17条では、古物市場主の取引の記録義務についての記載があります。
「古物市場主」とは・・・
古物商同士が取引する場所の提供をしたり、オークションの運営などを行いその入場料や手数料で儲けをだす事業者のことを指します。古物を直接売買しない点で「古物商」と異なります。
本記事では、古物商の方を対象として書いているため、ここでは説明を割愛します。
取引記録の例外
次の場合には、記録義務の全部または一部が免除されています。
①記録義務の全部が免除される場合
・買受け又は売却の対価の総額が1万円未満の取引(少額取引)の場合
※ただし盗品の混入を防止する必要のある一定の取引については、1万円未満であっても記録義務があります。
具体的にはバイク、テレビゲーム、書籍などです
・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける時
②売却の場合のみ記録義務が免除される場合
・国家公安委員会規則で定める古物を引き渡すとき
※ただし美術品類、時計、宝飾品類、自動車、バイク(原付含)は1万円未満でも記録は必要
③一部の記録事項について記録義務が免除される場合
・国家公安委員会規則で定める古物を引き渡したとき
⇒全国的に統一された法律上の登録制度が存在するため、引き渡しの相手方の記録義務を課さなくとも取引の相手方を特定することが可能なもの。具体的には自動車などがあります。
記録の保管義務について
古物営業法第18条には、古物商および古物市場主の帳簿等の備付義務について定められています。
具体的には、帳簿(台帳)に最後の記載をした日から3年間、営業所若しくは古物市場に備え付けておく(保管する)
電磁的方法による記録の場合も同様に3年間、直ちに書面を表示することができるように保存しておかなければなりません。
簡単にいうと、最後の記載をしてから最低でも3年間は残しておきなさい、というものですね。
また古物営業法第18条第2項には、仮に帳簿を紛失したり電磁的方法による記録が消えてしまったといった場合には、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならないとされています。
まとめ
・古物商は古物営業を行う際は、その取引の詳細を帳簿(台帳)に記載する必要がある
帳簿の形式は紙でも電磁的方法による記録(エクセルなど)でもOK
・取引金額が1万円未満の場合は記録が不要となる。但し例外あり
・帳簿は3年間の保管義務がある。
・もし帳簿を紛失した場合は速やかに所轄の警察署へ
お問い合わせはこちらから
いかがでしたでしょうか?
古物営業は帳簿の記載など付帯業務も多いため、しっかり抜けなくやっていきましょう。
また古物商申請や変更の届出など、ご自身で対応することが難しい方は、専門家に相談することをお勧めします。
弊所でも古物商申請に関するご相談は受け付けております。
問合せはこちらから↓