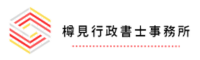こんにちは。行政書士の樽見です。
つい先日、ついに2025年度(令和7年度)の持続化補助金に関する詳細が発表されました!
2024年は早々に公募が終了してしまい、ずっと待ちぼうけとなっていた方もチャンスです。
しっかり詳細を把握した上で、公募開始を待ちましょう
※最新(2025年4月17日時点)情報
申請開始は5/1、締め切りは6/13です。商工会議所の支援を受ける補助金のため、お早めに動きましょう。
心配な方は問合せください。初回無料で相談受付中です。
類型や補助額、補助率について
持続化補助金の金額は①一般型、②創業型、③共同・協業型、④ビジネスコミュニティ型の4つがあります。
とはいえ過去の実績なども鑑みると、大抵の方は①一般型に該当されるかと思います。

1. 通常枠
通常枠は、本補助金の基本的な申請枠で、生産性の向上や販路拡大を目指す小規模事業者をサポートするものです。
おそらく大半の方がこの通常枠に該当します。
<補助額について>
補助額の上限は基本は50万円です。
ただし、特例要件の適用により、最大で250万円まで増額可能です。
<補助率について>
また補助率は基本的に2/3です。
(例えば75万円の支出を行った際、その2/3として50万円が補助の対象となります)
※ただし、賃金引上げ特例を適用した事業者のうち、赤字事業者の場合は3/4となります。
冒頭に特例適用で最大250万になる、と書きましたが以下がその特例です。
<特例要件>
・インボイス特例:免税事業者でインボイス発行事業者の登録を行った事業者⇒最大50万円上乗せ
・賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を50円以上引き上げた事業者⇒最大150万円上乗せ
⇒これにより、元々の50万に、インボイス特例の50万、賃金引上げ特例の150万が加わり250万円となります。
関連記事↓
では、実際にどういった事業に使えるのでしょうか?
公募要領には以下の通り記載があります。
<対象経費>
機械装置費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託費・外注費など
結構幅広く対象となっていますが、逆に言うと「これって補助対象になるの??」といった質問も多く出るポイントです。
ちなみに過去の経験から基づく経費支出の例としては、
製造業における機械装置の購入費、インターネット広告費、展示会出展費用、事業の為の旅費(交通費・ホテル代)、カメラマンに支払う費用などは認められています。
事務局への伝え方なども肝になってきますので、気になる方は私まで問合せください。
初回は無料で相談を受けておりますので、お気軽にどうぞ。
1点だけ例外を。
この一般型の中に、災害支援枠というものがあります。
対象は令和6年におきた能登半島地震における被災した小規模事業者です。
補助額の上限は、直接被害は200万円、間接被害は100万円です。
補助率は定額または2/3となっています。
対象経費は、機械装置費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託費・外注費、車両購入費です。
※災害支援枠のみ「車両購入費」が含まれています。
2. 創業型
創業型は、創業から3年以内の事業者が対象となります。新商品の開発や店舗のリニューアルなど、事業の拡大や販路開拓を支援します。
補助額の上限は200万円です。
ただし、インボイス特例の適用がありますので最大で250万円まで引き上げ可能です。
補助率は2/3です。
(通常枠のように賃金引上げ特例(且つ赤字事業者)が無いため、補助率は2/3のみ)
特例要件
免税事業者でインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円引き上げられます。
条件として「認定市区町村」からの支援が必要です。
対象経費
通常枠と同様、機械装置費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託費・外注費などが対象です。
※通常枠と同様です
3. 共同・協業型
共同・協業型は、地域振興機関が主導となり、10社以上の小規模事業者の商品やサービスの改善、ブランディング、販路開拓を目指す取り組みです。展示会や商談会、イベント販売、マーケティング拠点を活用し、地域全体の産業振興を推進します。
補助額の上限は最大5,000万円です。
補助率は、地域振興等機関に係る経費は定額、参画事業者に係る経費は2/3となっています。
(参画事業者は小規模事業者である必要あり)
- 対象経費
会場設営費や内装工事費、会場借料、機器・機材の借料、広報費、旅費など
4. ビジネスコミュニティ型
ビジネスコミュニティ型は商工会・商工会議所の内部組織等(例えば青年部、女性部等)を対象としたものです。
補助額は50万円。2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円となります。
補助率が定額なのが特徴の一つです。
- 対象経費
会場設営費や内装工事費、会場借料、機器・機材の借料、広報費、旅費など
※この記事を読んでいただいている方にとっては馴染みの薄い類型となりそうです。
前回からの変更点(抜粋)
前回の持続化補助金と比べ、大きな変更は無いように見受けられます。
一般型から「卒業枠」、「後継者支援枠」そのものが削除されました。
どんな人が対象(誰が申請できる?)
小規模事業者持続化補助金の申請ができるのは、中小企業および個人事業主です。
必ずしも法人である必要はありません。
従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、
製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者が対象です。
また申請にあたり近隣の商工会/商工会議所の協力を得る必要があります。
必ずしも商工会/商工会議所に入会している必要はありませんので、ご安心ください。
詳しく書いた記事は以下になりますので、ご参考まで。
持続化補助金の公募開始はいつ??
公募開始時期は現時点(2025年2月28日時点)ではまだ定かになっておりません。ただ事務局の人員募集が1月末であったりすることから、2025年3月末頃には公募開始されるかもしれません。
⇒現在(2025年4月17日時点)、公募要領の暫定版が公開されています!
申請受付開始は2025年5月1日、締め切りは2025年6月13日となっています。
どうやって申請するの??
小規模事業者持続化補助金は一般的な補助金と比べ、商工会/商工会議所の支援を受けなければならない点で異なります。
あらかじめ事業計画を策定した上で、その計画を商工会/商工会議所の担当者に共有し、「様式第4」といわれる書類を受け取る必要があります。
この「様式第4」は申請に必ず必要な書類です。申請者自身だけで作成することはできません。
そして最も大事な要素になるのは、事業計画書です。審査の判断はこの事業計画書でなされます。
今後どのようにして販路開拓していくのか?具体的な施策、それに伴う数値の推移、目論見などを整理して資料作成する必要があります。
まとめ
ついに始まる持続化補助金、前段にも書いた通り、申請にあたっては商工会の支援も必要ですが、まず第一に事業計画書の作成が必要です。
この事業計画書は、客観的な分析のもと、実行に値する施策を表記する必要があります。
持続化補助金の採択率は年々減少傾向にもあり、申請した事業者全員が補助金を受給できるわけではありません。
繰り返しますが、補助金の制度趣旨を理解し、具体的施策を策定、実行に伴う数値(売上や利益)の推移を簡潔にまとめる。これらをしっかりと取り組まなければなりません。
不採択となってしまうと、もうその回の持続化補助金には申請ができませんので、申請に少しでも不安を感じている方は、専門家に相談することをおすすめします。
問合せはこちらから
弊所(樽見行政書士事務所)でも、持続化補助金のご相談は随時受け付けております。
私自身もこれまで申請サポートはもとより、事業者(申請者)としても本補助金を採択~受給した経験がございます。
「読み手に分かりやすく、簡潔に且つ具体的に施策を説明する」ことに自信を持っておりますので、2025年の小規模持続化補助金申請を考えている方は一度ご相談ください。
まずはご自身が申請可能な状況にあるのかどうか?そこを無料で確認させていただきます。
お電話・zoom・対面などお選びいただけます。
問合せはこちらからどうぞ↓↓