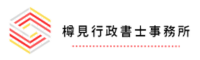こんにちは、行政書士の樽見です。今回は、2025年10月に施行される改正住宅セーフティネット法を活用して、賃貸オーナーが利用できる補助金についてまとめて解説します。
空室対策や高齢者・低所得者の入居支援に関心のある方にとって、補助金を上手に活用することは安定経営の大きなポイントになります。
目次
改正住宅セーフティネット法とは
住宅セーフティネット法は、住宅確保要配慮者(高齢者、低所得者、障害者、子育て世帯など)が安心して住まいを確保できるようにする法律です。2025年10月の改正により、以下のような仕組みが強化されます。
- 専用住宅(要配慮者専用の賃貸住宅)の登録制度の簡素化
- 家賃債務保証制度の創設
- 居住サポート住宅の新設(見守り・安否確認サービス付き)
- 残置物処理や入居中の支援強化
- 改修工事への補助制度の充実
賃貸オーナーが利用できる主な補助制度
改修費補助(最大200万円)
バリアフリー化、耐震改修、防火性能の向上、省エネ改修などに対して補助金が支給されます。自治体によっては1戸あたり最大200万円の補助が受けられます。
家賃低廉化補助(月最大4万円)
低所得者向けに家賃を相場より低く設定した場合、その減額分を自治体が補助します。空室を埋めつつ、収益を安定させることが可能です。
家賃債務保証料補助(上限6万円)
保証人がいない方の入居を円滑にするため、初回保証料を補助する制度です。入居拒否リスクを下げる効果があります。
見守りサービス・残置物処理の支援
居住支援法人との連携により、入居者の安否確認や死亡後の残置物処理に対応できます。大家側の不安を軽減できる制度設計です。
補助制度を活用するメリット
- 空室対策につながる
- 高齢者や低所得者の入居を受け入れやすくなる
- 改修費や保証料の補助でオーナー負担を減らせる
- 社会的評価が高まり、賃貸物件のブランド価値が上がる
利用するための流れ
- 自治体に専用住宅として登録申請
- 補助対象となる改修工事やサービスを導入
- 補助金交付申請書を提出
- 入居者の募集・契約
- 補助金の交付決定を受けて活用開始
注意すべきポイント
- 自治体ごとに補助金額・対象工事・要件が異なる
- 専用住宅登録には耐震性や面積などの条件がある
- 家賃補助や保証料補助には入居者の所得制限がある
- 管理期間(10年以上)が定められる場合が多い
今後の地域別記事へのリンク予定
本記事はまとめ記事ですが、今後は東京23区を中心に詳細記事も公開予定です。特に補助額が大きい区については詳細解説を予定しています。
- 北区(最大200万円)
- 荒川区(最大200万円)
- 豊島区(最大200万円)
- 墨田区(最大100万円)
- 渋谷区(最大200万円)
- 足立区
- 練馬区
- 世田谷区
- 港区
- 千代田区
各区ごとの詳細記事が公開され次第、本記事にリンクを設置しますので、ぜひチェックしてください。
行政書士へのご相談はこちら
補助金の申請には登録手続きや書類準備、工事内容の精査など専門的な対応が必要になります。
当事務所では、賃貸オーナーの皆さまの補助金活用をトータルでサポートしております。
- 登録手続きの代行
- 補助金申請の書類作成
- 自治体とのやりとり支援
お気軽にお問い合わせください。