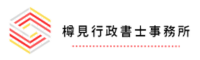はじめに
こんにちは。古物商の専門家、行政書士の樽見です。
この記事では、古物商、古物商申請について書いています。
はじめて「古物商」について調べた方、これから「古物商」の申請をやりたいけどよくわからない方に向けて書いています。これを読めば、古物商の取り方・申請書の書き方が分かります。
「中古品を売るには古物商が必要なんだよね?」
となんとなく知っている方は多いかと思いますが、
「どんな時に申請が必要なのか?」
「どうやって申請をするのか?」
この辺りに関してはよく分からない方も多いのではないでしょうか。
年間に数十万件の申請がなされる古物商ですが、まだまだ一般的な知名度は低いのも事実。
自分がやっている商売が実は古物商許可が必要だった・・!!ということのないよう、
最近流行りのメルカリを代表とするフリマアプリなどを継続利用されている方は、意識を高めてこの記事を読んでみてください。
古物商とは何か
さて、早速ですが「古物商」(こぶつしょう)とは何か?について説明していきます。
「古物商」とは、中古品や古物の売買、交換、または貸し借りを業務として行う事業者を指します。
古物商を営むには、「古物商許可」が必要です。この許可は、都道府県の公安委員会から発行されるもので、
許可なしに古物を取り扱う営業を行うことは法律で禁止されています。
これは、盗難品や不正品が市場に流通することを防ぐための法律「古物営業法」に基づいて定められています。
簡単に言うと、、
盗難品や偽物などがどんどん市場に出回ったりすることのないよう、公安委員会でしっかり管理します!
といった趣旨から古物商を営むには古物商許可が必要なんですね。
古物の13区分
「古物」というのは、一度使用された物や新品であっても一度人の手に渡った商品を意味し、その範囲は非常に広いです。
この古物には法律で定められた13の区分があり、それぞれ異なる種類の商品を指します。
これらの区分は、古物商が取り扱う商品の種類に応じてそれぞれ許可が必要です。
以下は、その13区分の概要です。
ご自身が扱おうとする商品がどの区分に該当するのか思い浮かべてみるとよいでしょう。
1. 美術品類 絵画、彫刻、工芸品などの美術品。 例: 絵画、陶器、骨董品、彫刻
2. 衣類 衣服や織物、履物などの服飾品。 例: 洋服、着物、バッグ、靴
3. 時計・宝飾品類 時計や宝石、貴金属類。 例: 腕時計、指輪、ネックレス
4. 自動車 自動車そのものや自動車の部品。 例: 自動車本体、タイヤ、エンジン部品
5. 自動二輪車・原動機付自転車 バイクやスクーター、およびその部品。 例: バイク、スクーター、バイクのパーツ
6. 自転車類 自転車やその部品。 例: 自転車本体、サドル、ハンドル
7. 写真機類 カメラやビデオカメラ、周辺機器。 例: カメラ、レンズ、ビデオカメラ
8. 音楽器類 楽器全般。 例: ギター、ピアノ、バイオリン
9. 家具類 家具やインテリア。 例: 机、椅子、ベッド、ソファ
10. 電気機械器具類 家電製品や電気機器。 例: テレビ、冷蔵庫、パソコン、エアコン
11. 工具類 作業工具や機械工具。 例: ドライバー、レンチ、電動ドリル
12. 書籍 本や雑誌などの書籍。 例: 小説、漫画、専門書
13. 皮革・ゴム製品類 皮革やゴム製の製品。 例: 革のカバン、財布、ゴム製の靴
古物営業とは
上で紹介した古物の売買や交換、レンタルを業として行うことを「古物営業」といい、古物営業を行う場合には、古物商許可(古物商許可証)が必要となります。
古物商許可の重要性
昨今、古物を取り扱う方が増えてきました。
EC(インターネット通販)市場に近年多くの方が参入してきています。
それは2025年現在もなおも変わらぬ勢いを保っています。
多くの方が古物を取り扱う世の中になったということは、色々な方がいます。
古物営業法では「古物」の取扱いについて法律として明文化されており、これらを遵守することで古物の適正な管理であったり、古物台帳の管理や警察への報告義務があるため、盗品や不正品の流通を抑止し、犯罪防止に寄与します。
古物商許可を取得していることは、法律を守り、適正な事業を行っている証となります。
特に、中古品やリサイクル商品を扱うビジネスでは、顧客の信頼が重要です。
許可があることで、取引先や顧客からの信頼度が高まり、事業の発展にもつながります。
古物商許可が必要なビジネスの例
それでは実際に、古物商許可が必要なビジネスにはどのような形態があるのか見ていきましょう。
リサイクルショップ
リサイクルショップでは、主に中古品を仕入れて再販売しています。
このような中古品やリサイクル品は、「古物」に該当します。古物営業法では、古物を売買、交換、または修理して再販売する業務を行う場合、古物商許可を取得することが義務付けられています。
したがって、リサイクルショップがこの許可を取得せずに営業することは、法律違反となります。
オンライン中古販売(ECサイト、フリマアプリ)
オンライン販売についてみていきましょう。
ここはケースバイケースですが、 中古品を継続的に売買して利益を得る場合です。
具体的には、個人であっても古物営業法に基づく「古物商」の要件を満たす取引を行う場合、許可が必要になります。
特に、以下の条件に該当する場合は、許可が求められます。
・継続的に中古品の仕入れと転売を行っている
・利益目的で、中古品を販売している 業務として古物を取り扱っている
例えば、リサイクルショップや、ネットショップ・メルカリを使って定期的に仕入れた中古品を販売する場合は、古物商許可が必要です。
反対に一般の個人が、家の不要品や使わなくなった商品をメルカリで売る場合は、古物商許可は不要です。
これには、以下のような場合が含まれます。
・自宅の不用品や不要になった私物を単発で販売する
・利益を目的とせず、単に物を処分するために売っている 。
このような場合、取引は趣味や不要品処分の範囲内であると見なされ、古物商許可の対象外となります。
実際のケースを通じて理解を深めていきましょう。
【古物営業法に抵触する可能性があるケース】
フリマアプリ上で次のような取引を行っている場合、古物商許可が必要な場合があります。
・新品を安く仕入れ、それを中古として販売する(たとえば、限定商品を大量に購入し、それを転売する)
・定期的に他人から中古品を買い取り、それを転売する オークションやフリマアプリを通じて仕入れた中古品を、別の販売チャネルで転売する。
これらは、営利目的かつ継続的な取引と見なされるため、古物商許可がないと法律違反に該当する可能性があります。
【法人や事業者の場合】
もし法人がフリマアプリを活用して中古品を売買する場合、古物商許可の取得がほぼ確実に必要です。企業として、定期的に中古品を取り扱っている場合、それは明確に業務の一部と見なされます。
骨董品の売買など
まず骨董品は法律上「古物」に該当します。
古物営業法において、「古物」とは一度使用された物品や、未使用でも使用のために取引された物品を指します。
骨董品も、通常は中古品として扱われるため、古物商としての許可が必要になります。
以下のようなケースでは、骨董品を取り扱うために古物商許可が必要です
営利目的で骨董品を売買する場合 骨董品を仕入れて、利益を得るために販売する場合、古物商許可が必要です。
これは骨董品店やオークションハウス、リサイクルショップ、個人事業主などが骨董品を取り扱う際に該当します。
継続的な取引を行う場合 個人や法人を問わず、継続的に骨董品を仕入れて販売する、あるいは販売目的でオークションに出品する場合も、古物商許可が求められます。
中古の骨董品を販売する場合 中古の骨董品、例えば絵画、陶器、古家具、時計、書籍などを扱う場合も古物商許可が必要です。
【許可が不要なケース】
骨董品に関しても、次のような状況では古物商許可は必要ありません
自分の所有する骨董品を単発で売る場合 個人が自分のコレクションや不用品として所有している骨董品を、単発で売却する場合は許可不要です。これはあくまで商業的な意図がない場合です。
相続した骨董品を売却する場合
→相続財産として得た骨董品を売る場合も、個人的な取引と見なされ、古物商許可は不要です。
古物商許可申請のステップ
ここからは実際に古物商許可申請にあたって、確認すべきことや具体的な手順をご説明します。
申請の前に確認すべき要件
申請にあたり、予め確認してしておくべき要件があります。
これらの要件を満たしていないとそもそも申請しても許可がおりませんのでご注意ください。
欠格要件
ここからは欠格要件についてご説明します。
以下の項目に1つでも該当する人がいる場合、許可を受けられません。
※読んでもイマイチ分からない・・という方は、本記事では一旦読み飛ばして専門家に聞いてみましょう。
・成年被後見人または被保佐人 判断能力が著しく欠如していると法的に認められた者は、古物商の許可を取得することができません。
・破産者で復権を得ていない者 破産手続き中の者、または破産したが未だに復権を得ていない者は、許可が下りません。
・禁固以上の刑に処せられている者、過去に禁固以上の刑を受けて刑の執行が終わっていない、または執行猶予中の者は、許可が与えられません。ただし、執行猶予が満了した場合や、刑の執行が完了した後は許可の対象となる可能性があります。
・特定の犯罪歴がある者
→窃盗、強盗、詐欺、背任などの財産に関する犯罪 違法薬物、暴力団関係、その他反社会的行為に関する犯罪 暴力団関係者やその関係者 申請者が現在暴力団員である場合、または過去5年以内に暴力団員であった場合、許可は下りません。また、申請者が暴力団員と密接な関係を持っていると判断された場合も、許可が拒否される可能性があります。
・許可取消後5年を経過していない者 過去に古物商許可を受けていたが、許可を取り消された者は、取消から5年が経過していない場合は新たに許可を取得することができません。
・住居不定の者 申請者が住居不定の場合、古物商許可の申請が受理されません。安定した住所を持っていないと、業務の安定性や信頼性が疑われるためです。
適正な管理者がいない場合 古物営業を行うためには、申請者が管理者として適正な人物であることが必要です。もし申請者が法人であれば、法人の役員や業務を管理する者もこれらの要件を満たす必要があります。
営業に関して重大な違法行為を行った法人や個人 古物営業に関連して、重大な違法行為を行った法人や個人も、一定期間古物商の許可が受けられない可能性があります。
住民票や税証明など、必要書類の確認
必要書類は以下になります。
1. 申請書 古物商許可申請書(公安委員会の指定様式) ※後ほど詳しく解説します
2. 身分証明書と住民票:本籍地が記載されているもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。市区町村役場で発行。 身分証明書:本籍地の市区町村役場で発行されるもので、成年被後見人・破産者でないことを証明する書類。
3. 登記事項証明書 法人の場合は法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書。個人事業主の場合は必要ありません。
4. 税証明書 所得証明書(または納税証明書):市区町村役場で発行される所得に関する証明書。 直近の納税証明書:個人の場合、税務署から発行される納税証明書も必要になることがあります。
5. 誓約書 申請者本人および管理者が、法令違反やその他の不適格者でないことを誓約する書類。
6. 登記されていないことの証明書 法務局で発行され、成年被後見人や保佐人でないことを証明する書類。
7. 住居関係書類 申請者の住民票の住所が異なる場合、営業所の所在地の確認書類(賃貸契約書など)が必要。
8. 略歴書 申請者や管理者の略歴を記載する書類。
9. 営業所の使用権限を証明する書類 営業所を賃貸する場合は賃貸借契約書の写しなど、使用権限を証明する書類。
10. 管理者の承諾書 申請者とは別に管理者を置く場合、その承諾書が必要です。 これらの書類を準備し、公安委員会へ提出する必要があります。
また、申請料としておおよそ19,000円が必要です。
法人と個人事業主で異なる手続き
古物商許可申請において、法人と個人事業主では手続きの基本的な流れはほぼ同じですが、いくつか異なる点があります。ここではそれぞれの違いについて詳しく解説します。
1. 申請者の違い
法人の場合 申請者は法人となり、代表者や役員、管理者に関する書類を提出する必要があります。申請書には法人情報が記載され、法人の代表者が責任者として申請を行います。 個人事業主の場合 申請者は事業主本人となります。個人事業主の場合、事業主本人がすべての責任を負い、手続きを進めます。
2. 必要書類の違い
<法人の場合>
法人の申請では、法人特有の書類が追加で必要になります。
法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
→法人であることを証明するため、法人の登記簿謄本または履歴事項全部証明書を提出する必要があります。これは法務局で取得します。
定款の写し
→法人設立時に作成した定款の写しを提出します。定款には法人の目的が記載されており、その中に「古物商に関する業務」が含まれていることが必要です。
役員に関する書類
→すべての役員に関して、個人事業主と同様の書類(住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書など)を提出する必要があります。これは、役員も法令違反などに該当しないことを確認するためです。
<個人事業主の場合>
→個人事業主では、法人に必要な書類が不要です。 登記簿謄本や定款 個人事業主の場合、法人ではないためこれらの書類は不要です。 略歴書 個人事業主の場合、事業主本人のみの略歴書を提出します。
3. 管理者の設置
<法人の場合>
法人は、古物商営業の管理者を選任し、その人に関する書類も提出する必要があります。管理者は古物営業に関する実務を担当し、法律を遵守する役割を持っています。管理者は法人の役員でなくてもかまいませんが、申請時に管理者として適切かどうかを審査されます。
<個人事業主の場合>
個人事業主自身が管理者となることが一般的です。別途管理者を選任する場合は、その人に関する書類が必要です。
4. その他の違い
申請書の内容
法人では「法人名」「代表者名」「本店所在地」を記載しますが、個人事業主の場合は「事業主名」「営業所所在地」を記載します。 費用 法人と個人事業主で申請費用は基本的に同額です。どちらも申請手数料として約19,000円を支払います。
申請書の記入方法
ここでは実際に古物商申請に提出する書類の記入方法について説明していきます。
添付書類の確認(身分証明書、住民票、登記簿謄本など)
添付の書類を揃えたら、次は申請書の作成です。
ここからは申請者自身の情報をご自身で記入する必要がありますので、間違いなくいきましょう。
その前にまず、申請書一式はどこでもらえるのか?
各都道府県の公安員会のホームページからダウンロードできます。 ホームページからのダウンロード以外にも、実際に警察署に行ってもらうこともできます。
さらに事前にアポイントを取ることで「生活安全課」の古物担当の方とコミュニケーションを取ることもできます。
準備する申請書の様式は次の通りです。
①別記様式第1号その1(ア)(第1条関係)-古物商許可申請書
②別記様式第1号その2(第1条関係)-営業所情報
③別記様式第1号その3(第1条関係)-URLの届出 法人申請の場合は追加で以下が必要です
④別記様式第1号その1(イ)(第1条関係)-法人役員 ※ 別記様式第1号その1(イ) は、様式1枚につき3名までの記載でます。役員がそれ以上いる場合は複数枚必要となります。
なお、①の書類については現在では、押印が不要となりました。 他にも押印不要なものとして、「略歴書」、「誓約書」があります。 また追加情報ですが、場合によっては警察署から追加書類を求められる場合があります。
・URL疎明資料(whois情報やプロバイダからのユーザー証明) ※インターネットを用いて古物を販売している方は注意
・賃貸借契約書の写し
・周辺地図や営業所の図面
このあたりは管轄警察署の担当者さんと密にコミュニケーションを取りながら、慎重にチェックしましょう。
申請窓口への提出
添付書類から申請書まで全て揃えたら、実際に警察署に提出! と行きたい所ですが、その前にしっかり副本を作成しておきましょう。 副本とはいわゆるコピーのことです。漏れなくしっかりコピーをとりましょう。
また古物商許可申請は、申請書を提出してから許可まで40日程度かかります(土日祝除く)。これを審査期間と言ったりします。 準備した添付書類は、作成日付が申請日から3か月以内のものでなければなりません。
都道府県の警察署または公安委員会に提出
作成した書類は管轄警察署の「生活安全課 防犯係」になります。
警察署によって、担当者を置いていることがほとんどですので、予めその担当者がいるかどうか、電話で問い合わせておきましょう。 担当者不在だと、受け取ってもらえなかったりスムーズに進まない可能性もありますので、ここは確実にいきましょう。
電話口では「古物商許可申請の書類を揃えましたので、提出に伺いたいです」と伝え、日程調整をしましょう。 ちなみに受け付けてもらえるのは平日の日中のみです。行くことが難しい人は専門家にお願いすることを検討しましょう。
手数料の支払い方法
古物商許可申請には申請手数料19,000円が必要です。
県の証紙を購入する場合や、申請書が受理された後に現金で購入する場合などがあります。
※最近ではクレジット払い可能な警察署も増えてきました。
詳しくは管轄警察署の担当者に確認しておきましょう。
提出後の審査期間
申請書が無事に受理されると「その翌日から起算して40日間」が標準処理期間といって、この処理にかかる目安の日数です。
勿論この日数はあくまで目安ですので、早まることもあります。
審査の際の注意点
古物商申請における警察署の「審査の際の注意点」は、申請書類の正確性と適法性が最も重要です。
まず、申請者の身元や事業内容がしっかり確認されます。申請者が反社会的勢力と関係がないか、過去に犯罪歴がないかも審査の対象となるため、身分証明書や住民票などの提出書類は最新のものである必要があります。
また、営業所の所在地が法律に準じているか、申請する事業が実際に運営できる環境であるかも確認されます。例えば、住居専用地域での営業所開設は許可されない場合があるため、物件の用途地域の確認も必要です。
申請が却下されるケース
せっかく申請を出したのに却下されてしまうケースもあります。
正しい手続きを取ったつもりになっていても、いざ実際に書類を提出すると想定していなかったことが起こります。
書類不備
古物商申請が却下される主な理由の一つは書類不備です。
具体的には、住民票や登記簿謄本の記載内容が最新でない場合や、身分証明書が期限切れの場合、申請書類の必要な欄が未記入であったり、誤記がある場合です。
法的要件の不適合
古物商申請で法的要件に不適合となる主なケースは、申請者が古物営業法やその他関連法規を満たしていない場合です。
例えば、過去に重大な犯罪歴がある場合や、反社会的勢力との関係があると判断された場合、法的に不適格となります。また、申請者の年齢が未成年の場合や、日本国内に住民登録がない外国籍者も不適合です。さらに、営業所の所在地が住居専用地域で、古物営業が認められない場合も要件不適合となります。
犯罪歴や違反歴のある場合の対応
古物商申請において、犯罪歴や違反歴がある場合でも、必ずしも申請が通らないわけではありませんが、厳しい審査が行われます。特に、重大な犯罪(暴力犯罪、窃盗、詐欺など)や反社会的勢力との関係がある場合は、許可が下りない可能性が高いです。
古物営業法における具体的な不許可事由には、過去に懲役や罰金刑を受けた場合や、古物営業法に違反した経歴が含まれます。
しかし、過去の違反や犯罪が軽微なものであり、かつ長期間が経過している場合には、申請が通る可能性もあります。このような場合、申請者が反省して社会復帰していることや、今後の法令遵守の意思を示すことが重要です。
許可後の義務と手続き
古物商許可は取って終わりではありません。
無事に古物商許可がおりた場合、その後もやることがありますのでしっかり対策していきましょう。
古物台帳の作成・管理方法
古物台帳は、買取や販売した物品の詳細(品目、日付、相手方の情報)を記録するための帳簿です。適切に作成・管理し、警察の求めに応じて提示できる状態にしておく必要があります。
【別記事:古物台帳について】
買取品の管理と報告
商売に用いるために買取した古物は一定期間保管し、速やかに盗品や犯罪関連物ではないか確認します。不審物が発見された場合は、速やかに警察に報告する義務があります。
変更申請や定期的な監査
古物商許可は有効期限がありません。つまり一度取得するとずっと継続して営業をすることができます。
ただし、営業内容の変更や廃止があった場合には報告が必要です。また会社の代表者や役員、住所、名称、営業所の新設・閉鎖などに変更があった場合は変更申請が必要となります。
また、定期的な警察の監査を受け、営業を適切に行っているか確認されます。
当然、法令遵守が確認されない場合、指導や罰則が科される可能性があります。
【別記事:古物商許可における変更申請が必要な場合】
古物商許可申請にかかる費用と時間
すでに古物商許可申請にかかる費用は前項の方で説明済ですが、
申請費用(都道府県ごとの違いは?)
古物商許可申請の費用は、基本的に19,000円です。(全国一律)
都道府県による差はありません。
支払い方法については、申請時に警察署の窓口にて支払う形となります。
許可取得までの期間
古物商許可は、申請から許可が下りるまで通常40日程度かかります。
ただし、警察署の審査が厳しい地域や、書類不備があった場合はさらに時間がかかる可能性があります。特に、申請者の経歴調査や営業所の場所確認が必要な場合、追加の時間を要することもあります。したがって、申請から許可が下りるまで余裕をもって計画することが大切です。
警察署ごとに独自色を出しているケースが多く、思いがけない書類が必要となる場合も稀にありますので、事前に警察署に連絡を入れ、何が必要かを確認しておくとよいでしょう。
追加費用や注意事項
古物商許可の申請自体には大きな追加費用はかかりません。
強いていうならば、申請の際に取得する住民票などの帳票取得にかかる費用があります。(数百円程度です)
古物商許可が必要かどうかの判断基準
- 中古品を一時的に扱う場合の対応
中古品を一時的に扱う場合でも、古物商許可が必要になるケースがあります。例えば、短期間だけでも中古品を買い取って販売するビジネスを行う場合は許可が必須です。ただし、自己使用のために一度購入した品を再び売却する場合や、単なる不要品の売却は古物営業に該当せず、許可は不要です。継続して事業として中古品を扱う場合は、必ず古物商許可を取得する必要があります。
- 例外事項と特例措置
古物商許可が不要な例外事項もあります。例えば、リサイクルショップなどが新品商品を取り扱う場合や、個人が趣味でコレクション品を売却する場合などは、古物商許可が必要ありません。また、地方自治体が主催するイベントでの一時的な出店や、特定の団体に限定されたフリーマーケットも例外的に許可が不要とされることがあります。特例措置や例外に該当するかどうかは、各自治体の規定や警察署で確認するのが確実です。
古物商申請を専門家に依頼するメリット
ここまで古物商許可申請、及び申請方法について書いて来ました。本記事の説明の通りに行うことでご自身で申請することも可能です。
ただ書類の取得不備、申請書の記載は意外と記入漏れが多く、さらには平日の日中のみ受付のため時間の都合をつけられない方が多いのも事実です。
対応が難しい方は専門家への依頼を検討しましょう。
自分で行う申請と専門家に依頼する場合の違い
自分で古物商申請を行う場合、必要な書類の準備や提出先の確認、警察署での手続きなど、すべてを自分で調べて行わなければなりません。一見簡単に思える手続きでも、書類の記入漏れや不備、法律に関する理解不足が原因で却下されるケースも多々あります。一方、専門家である行政書士に依頼することで、書類の不備を防ぎ、スムーズに申請手続きを進めることができます。行政書士は法律知識を備えているため、正確で迅速な対応が期待できるのです。
時間の節約、法的リスクの軽減
古物商申請には、細かな書類の準備や提出、審査期間の管理が必要で、これには多くの時間と手間がかかります。特に本業を抱える事業主にとって、申請業務に時間を取られるのは大きな負担です。
専門家に依頼することで、この手間を省き、申請手続きを効率的に進めることが可能です。また、法的なリスクも軽減できます。法律や規則を正しく理解し、適切に対応するための専門知識がないと、思わぬトラブルが発生することがありますが、行政書士に依頼すれば、そうしたリスクを回避できます。
相談料や手数料の相場
行政書士に古物商申請を依頼する際の費用は、一般的に数万円程度です。相場は地域や依頼内容によって異なりますが、5万円前後が一般的です。一見、自分で申請すれば費用を抑えられるように思えるかもしれませんが、書類不備や再提出による遅延、トラブル対応にかかる時間や労力を考えると、専門家に依頼することで得られる安心感やスムーズな手続きは十分に価値があります。手数料以上に、時間と安心を得られる点が大きなメリットです。
特に書類不備などが重なり警察署に3度、4度と行くことで時間的にかなりロスになってしまい、始めたい商売が始められないということがよくあります。
ちなみに弊所では以下の通り、3つの料金形態をご用意しております。

どのプランであっても申請書の作成や警察署との電話での打合せはこちらで代行いたしますのでご安心ください。
一度問合せ頂きますと申請がスムーズです。
問合せはこちらから↓