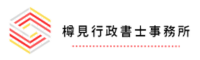「古物商許可申請」の提出先は「管轄の警察署 生活安全課 防犯係」
古物商許可申請の際、申請書を提出する場所は、管轄警察署の生活安全課内の防犯係です。この申請が警察署を通じて行われるため、「どんな質問をされるのだろうか」、「ちゃんと受け付けてもらえるだろうか」と不安を感じている方もいるかもしれません。
今回は、古物商許可申請における警察署での手続きや対応について解説します。これから申請を行う方にとって、少しでも役立つ情報になるかと思います。
申請書・添付書類の整理
古物商許可申請書と必要な添付書類が揃ったら、まずは記載ミスや不足書類がないかを丁寧に確認しましょう。古物商許可申請では、全ての必要書類が揃っていないと受理されません。不備があると何度も警察署に出向かなければならなくなるため、申請書類のチェックは慎重に行いましょう。
申請書提出の予約
申請書を提出する前に、必ず管轄警察署の生活安全課防犯係に電話をして、提出の日時を予約します。
「申請書類が揃いましたので、提出に伺いたいです」と伝え、個人または法人の申請内容も併せて説明するとスムーズです。警察署によっては希望の日程で予約が取れない場合もあるため、いくつか候補日を用意しておくと良いでしょう。
なお、警察署によっては予約が不要な場合もありますが、その際も事前に連絡を入れておくのが望ましいです。申請の際には書類の確認や手数料の支払いもあるため、全体で30分ほどの時間を見込んでおく必要があります。
申請時に持参すべきもの
申請書の提出時には、以下のものを忘れずに持参しましょう。
- 申請書類一式(正本・副本)
- 申請手数料 19,000円
- 身分証明書
- 印鑑
- 委任状(代理人が申請を行う場合)
申請書類一式
申請書は、原本と副本の2部を提出します。事前に自分用の控えも作成しておくと安心です。
申請手数料
都道府県ごとに納付方法が異なるため、事前に確認が必要です。東京都では現金での支払いが一般的ですが、他県では「県の証紙」が必要な場合もあります。
身分証明書
申請者の本人確認書類が必要です。免許証や保険証を持参しましょう。
印鑑
申請書に使用した印鑑を持参します。法人の場合は代表者印が必要です。不備があった場合、訂正印が必要になるため、印鑑を忘れずに持っていきましょう。
委任状
代理人が申請を行う場合には、申請者からの委任状が必要です。
警察署までのアクセス
警察署によっては駐車場が少ないため、できるだけ公共交通機関を利用しましょう。警察署までのアクセスは事前に確認し、時間に余裕をもって向かうことが大切です。
質問対策の事前準備
申請書提出時には、警察署の担当者から質問を受けることがあります。予想される質問の一例としては、次のようなものがあります。
- どこから古物を仕入れる予定ですか?
- 店舗を構えますか?
- 過去に古物商の経験はありますか?
しっかりと回答できるよう、事前に準備しておきましょう。
警察署に到着したら
予約した日時に警察署に到着したら、まず「受付」に向かい、「古物商の申請で来ました」と伝えましょう。警察署によっては、受付がない場合もありますので、その場合は近くにいる署員に声をかけてください。
案内されたら、生活安全課の窓口へ進みます。そこで申請書類を提出することになります。
自信をもって申請を行いましょう
申請窓口で書類を提出したら、担当者が書類を確認します。この際、書類に不備があった場合、訂正や補正が求められることもあります。可能な限り事前準備をしておくことが大切ですが、その場での対応が必要になる場合もありますので、落ち着いて自信を持って対応しましょう。
申請書受理後は申請手数料の納付
申請書が無事に受理されると、次に申請手数料(19,000円)を支払います。支払い方法は警察署によって異なるため、担当者の指示に従って納付しましょう。
納付後に受け取る「領収書」や「受領書」は大切に保管してください。場合によっては、申請書の控えに受領印を押してもらえることもありますので、必要に応じて担当者に確認すると良いでしょう。
受理後の40日間
申請書が受理された後、審査は「その翌日から40日間(土日を除く)」かかります。この期間は、古物商許可の標準処理期間とされており、警察による審査が行われます。
この期間中に、警察署が営業所の確認に訪れることもあり、表札やポストの設置状況などが確認されることもあります。必要な指摘を受けた場合は、速やかに対応しましょう。
古物商許可証の交付
審査が無事に終了すると、管轄警察署から許可証の交付準備が整った旨の連絡があります。連絡を受けたら、指定された日時に警察署の生活安全課防犯係へ行き、古物商許可証を受け取ります。
許可証を受け取る際には、次のものを忘れずに持参しましょう。
法人代表者印
法人の場合、代表者が受け取る際には法人代表者印が必要です。
印鑑
許可証の受領の際に署名が求められるため、認印を持参しましょう。
身分証明書
本人確認のため、免許証や保険証などの身分証明書を持参してください。
筆記用具
許可証の交付時に説明を受けることがあり、古物営業に関するガイドブックなども渡されます。必要に応じて、メモを取れるよう筆記用具を持っていきましょう。
委任状
代理人が許可証を受け取る場合、申請者からの委任状が必要です。委任状には「許可証の受領に関する権限」を記載しておきましょう。
お問い合わせはこちらから
いかがでしたでしょうか?
事前準備をしっかりやれば、そこまで怖くないはずです。
ただどうしても時間が取れない・・・
申請書の書き方がいまいち分からない・・・
といった方は迷わず専門家にまずは相談することをお勧めします。
弊所でも古物商申請に関するご相談は受け付けております。
問合せはこちらから↓