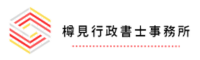新たに営業所を開設することが決まり、古物商許可が必要な状況に直面した際に、
「申請はいつすればいいの?」、「許可が下りるまでどのくらいかかるの?」、「自分でやるべきか、それとも行政書士に頼むべき?」などの疑問を抱く方も多いでしょう。
この記事では、そういった疑問を持つ方のために解説しています。
古物商許可の取得に要する期間はどのくらい?
古物商許可を申請する際には、まず必要書類を集め、次に申請書を完成させ、それを管轄の警察署に提出する流れになります。申請が受理されると、警察署での審査が開始され、標準的な処理期間は約40日程度かかります。申請の準備がスムーズに進んだ場合でも、全体で2か月ほどの時間を見ておくとよいでしょう。
標準処理期間(審査期間)とは?
標準処理期間とは、申請が受理されてから許可が下りるまでの目安となる期間を指します。古物営業法第3条第1号によると、古物商許可の標準処理期間は40日と定められています。
40日の期間は、申請をした翌日からカウントされ、土日や祝日、年末年始は含まれません。警察署によっては、40日よりも早く許可が下りる場合もあります。
申請書を自分で作成する場合の手順
自分で古物商許可を取得しようとする際、まず申請書の記入を始める方が多いかもしれませんが、実際には必要書類を揃える順番が重要です。この順序を間違えると、無駄な時間を浪費してしまうことがあります。
必要書類を揃えるための期間
まず最初に取得すべきなのは「住民票」でしょう。ただし、住民票や他の証明書は平日の昼間しか窓口で取得できませんし、郵送で請求する場合は到着まで2〜3日かかることがあります。また、「住民票」と一致する情報が必要な「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」も、住民票を取得してから請求するのが望ましいです。これらの書類が揃うまでには郵送で5日~7日程度かかります。
1日で全ての書類を揃えるには、各役所に足を運ぶ必要があり、手間はかかりますが、可能ではあります。また、法人登記簿など他の書類も集める必要があり、書類の準備にそれなりの時間がかかるでしょう。
なお、令和元年12月14日以降、「登記されていないことの証明書」の提出が不要になったので、この点にご注意ください。
申請書の記載方法
必要書類を揃えたら、古物商許可申請書の記載に進みます。以前に古物商許可を取得した経験がある方なら、申請書の記載もスムーズに進められるでしょう。しかし、初めての場合は記載例を見ながら進めても、不明点が出てくることがあり、警察署に問い合わせをするなど、多少時間がかかることがあります。1日で終わらない場合もあれば、数日かかることもあります。
行政書士に依頼した場合の流れ
経験豊富な行政書士に依頼すれば、書類の準備や記載も迅速に進められ、最短で申請後5日程度で警察署に提出することも可能です。受理後は標準処理期間の40日が経過すると許可証が発行され、全体で約1カ月半から2カ月で古物商許可を取得できるでしょう。
スピードを優先しない行政書士の場合、提出までに2~3週間かかることもあります。早く許可を取得したい場合は、2カ月の余裕を持ち、スピード重視の行政書士に依頼することが推奨されます。
申請手続きはいつから開始できる?
古物商許可申請を行う際、まず営業所を確定する必要があります。自宅を営業所にする場合は必要書類が少なく済むことがありますが、賃貸物件を営業所にする場合は「賃貸借契約書」が必要です。契約が完了していない段階では申請はできません。
また、法人の場合は「履歴事項全部証明書」が必要なので、法人設立後、登記が完了していない時点では申請できません。営業所の選定や法人設立などは、古物商許可申請のための重要な前提条件です。
まとめ
古物商許可を取得するには、申請準備から許可証の発行まで約2か月かかります。
- 申請準備:7日以上
- 審査期間:土日を除く約40日
行政書士に依頼すれば、最短で申請を提出することができ、許可取得までの時間を短縮できます。賃貸物件や法人の場合は、契約や設立手続きが完了していないと申請できない点にも注意が必要です。
お問い合わせはこちらから
いかがでしたでしょうか?
事前準備をしっかりやれば、そこまで怖くないはずです。
ただどうしても時間が取れない・・・
申請書の書き方がいまいち分からない・・・
といった方は迷わず専門家にまずは相談することをお勧めします。
弊所でも古物商申請に関するご相談は受け付けております。
問合せはこちらから↓