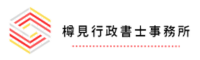古物商許可を取得できるのか?
これから古物商許可の取得を考えている人の中には、「自分が許可を取得できるのかどうか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。また、具体的にどのように確認すればよいのかがわからず、困っている場合もあるかもしれません。
実際、古物商許可が取得できるかどうか(欠格要件)を調べてみても、法律の内容が複雑で、理解しにくいと感じる方もいるでしょう。
古物商許可は、どれだけ完璧な申請書類を揃えても、全ての人が取得できるわけではありません!
そこで今回は、古物商許可を取得できる場合と、取得が難しい場合について詳しく見ていきましょう。
古物商許可が取得できない人とは?
古物商許可を取得できない人は、どのような条件に該当するのでしょうか?
実は、古物営業法第4条に定められている欠格要件に1つでも該当する場合、許可を受けることができません。この条文には、様々な項目が細かく規定されており、これに該当する人は許可が下りないということになります。
古物営業法第4条(欠格要件)とは?
「第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を申請した者が次の条件のいずれかに該当する場合、許可を与えてはならない。」という内容です。
この条文の通り、いずれかの条件に該当すると、許可が下りることはありません。それでは、具体的な条件を見ていきましょう。
【1. 破産手続き中で復権を得ていない人】
「破産手続き中で復権を得ていない」とは、自己破産手続きを開始してから、その後の免責が認められていない状態を指します。復権が認められれば古物商許可を取得することができますが、それまでは申請することができません。
【2. 禁錮以上の刑に処せられた人】
「禁錮以上の刑」とは、禁錮刑、懲役刑、そして死刑などが該当します。これらの刑を受けた人は、刑の執行後5年間、許可を取得することができません。ただし、執行猶予期間が終わった場合には、許可を取得できるようになります。
【3. 集団的または常習的に暴力行為やその他の違法行為を行う恐れがある者】
警察は、申請者が暴力団や違法行為に関与する恐れがあると判断した場合、古物商許可を拒否します。特に暴力団の関係者や、それに類する行為を常習的に行う人物は、社会の安全を脅かす存在として警戒されています。このような理由から、反社会的勢力と認められる可能性がある場合には、申請は通りません。
【4. 暴力団員等に関する規定に違反した者】
暴力団員やその関係者に対して、古物商許可は厳しく制限されています。「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴力団排除条例)の規定に基づき、特定の命令や指示を受けた者は、その命令から3年が経過していない限り、許可を取得することができません。暴力団員だけでなく、その命令を受けた者も制限対象となります。
【5. 住所が定まっていない者】
住居が不安定であったり、住所不定である場合も許可は下りません。これは、古物商の営業活動が安定して行われない恐れがあるためです。住民票に記載されている住所に居住していることが基本ですが、事情により異なる住所に住んでいる場合は、事前に行政書士に相談することで解決策が見つかることもあります。
【6. 過去に古物商許可を取り消された者】
古物営業法第24条に基づき、過去に古物商許可を取り消された者も、取り消しから5年間は新たな許可を受けることができません。これは、以前に法令を守らず、適正に営業を行わなかった者が、再び同じ過ちを犯すリスクを防ぐためです。法人の場合、取り消しの時点で役員であった者も同様に5年間の制限が適用されます。
【7. 許可の取消しが決まる前に許可証を返納した者】
許可の取消しが確定する前に、自ら許可証を返納した場合も、5年間は許可を再取得することができません。これは、許可の取消しを避けるために意図的に許可証を返納した場合に適用される規定です。
【8. 心身の故障により業務を適正に行えない者】
古物商や古物市場の業務を適切に遂行できない心身の故障がある場合、古物商許可は下りません。これには、成年被後見人や、精神的・身体的な障害があると判断された場合が含まれます。令和元年の法律改正により、この規定が明確化されました。
【9. 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者】
未成年者は原則として古物商許可を取得することができません。ただし、未成年者が古物商や古物市場主の相続人であり、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合は例外となります。また、結婚によって成年擬制が適用される未成年者や、法人での申請において未成年者が役員である場合は、法人として許可を受けることが可能です。
【10. 営業所ごとの管理者が適任でない者】
古物商許可の取得に際しては、営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。選任された管理者が欠格要件に該当する場合、許可は下りません。管理者には、古物営業を適正に行うための知識や技術が求められ、また、管理者が営業所に通勤可能な距離に居住していることが必要です。警察は、この管理者が適任かどうかを慎重に審査します。
【11. 法人の役員の中に欠格要件該当者がいる場合】
法人で古物商許可を申請する際、役員の中に上記の欠格要件に該当する者がいる場合、許可は下りません。法人の全役員がこの条件を満たすことが必要であり、該当者が一人でもいる場合は許可申請が却下されます。
欠格要件に該当しない人とは?
欠格要件に該当しない場合、古物商許可を受けることが可能です。例えば、軽い交通違反などの道路交通法違反で罰金を受けた場合や、執行猶予が満了した後であれば、問題なく許可を申請できます。
また、役員に該当する欠格要件者がいる場合でも、その役員を辞任させることで許可を受けることができるケースもあります。
まとめ
- 古物商許可は誰でも取得できるわけではありません。
- 許可を申請する際は、事前に欠格要件を確認することが重要です。
- 判断に迷ったら、専門の行政書士に相談することをお勧めします。
古物商許可をスムーズに取得するためには、欠格要件について正しく理解し、適切な手続きを進めることが重要です。
お問い合わせはこちらから
いかがでしたでしょうか?
事前準備をしっかりやれば、そこまで怖くないはずです。
ただどうしても時間が取れない・・・
申請書の書き方がいまいち分からない・・・
といった方は迷わず専門家にまずは相談することをお勧めします。
弊所でも古物商申請に関するご相談は受け付けております。
問合せはこちらから↓