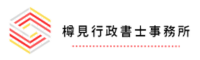古物商許可申請には3種類の証明書が求められます。
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
今回は、特に混同しやすい「身分証明書」について解説します。
古物商許可申請に必要な身分証明書は本人確認書類ではない
古物商許可申請に必要な「身分証明書」を準備する際に、運転免許証や保険証などのコピーを用意する方もいるかもしれませんが、この「身分証明書」は本人確認のためのものではありません。
申請者の本籍地が所在する市区町村の役所が発行する、以下の3項目を証明するための書類です。
- 禁治産や準禁治産の宣告を受けていないこと
- 後見の登記がされていないこと
- 破産宣告または破産手続開始決定を受けていないこと
禁治産・準禁治産とは?
禁治産は「心神喪失の状態」、準禁治産は「心神耗弱や浪費癖」を指します。1999年の民法改正で廃止され、現在は成年後見制度に基づく判断能力に関する要件へと移行しています。
後見登記とは
裁判所の審判により「後見登記等ファイル」に登録され、精神的な障害を理由に後見制度の適用を受ける際に必要となる登記です。
破産宣告・破産手続開始の決定
2004年の新破産法制定により、かつての「破産宣告」は「破産手続開始決定」として扱われます。破産者で復権を得ていない人を指し、復権が許可されれば古物商許可の申請も可能となります。
「身分証明書」の取得方法
本籍地の市区町村役場で取得可能で、本人または委任状を持った代理人が請求できます。本籍地が遠方の場合でも郵送で請求できるため、事前に余裕をもって手続きを行うと良いでしょう。
古物商許可の申請では、申請者や管理者全員分の「身分証明書」が必要です。本籍地が遠い場合や取得手続きが負担に感じる方は、行政書士に依頼することも選択肢のひとつです。
外国人申請者の場合
申請者が外国人の場合は日本に本籍地がないため、「身分証明書」を取得できませんが、申請は可能です。代わりとなる書類や特例については、管轄警察署や行政書士に事前確認を行いましょう。
「身分証明書」が必要な理由
古物営業法の規定により、成年被後見人や破産者など欠格事由に該当する場合は許可が下りません。身分証明書を提出することで、これらの欠格事由に該当しないことを証明することが求められます。
まとめ
- 「身分証明書」は本人確認ではなく、欠格事由に該当しないことを証明する書類です。
- 本籍地の市区町村役場で取得可能。
- 申請者および管理者全員分が必要。
- 取得手続きが負担になる場合は行政書士に相談することもおすすめです。
古物商許可の申請には準備すべき書類が多いため、事前の確認と計画的な手続きが大切です。
お問い合わせはこちらから
いかがでしたでしょうか?
事前準備をしっかりやれば、そこまで怖くないはずです。
ただどうしても時間が取れない・・・
申請書の書き方がいまいち分からない・・・
といった方は迷わず専門家にまずは相談することをお勧めします。
弊所でも古物商申請に関するご相談は受け付けております。
問合せはこちらから↓