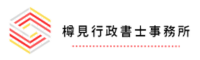古物商許可申請には、「略歴書」と呼ばれる書類が必要です。申請者や法人の役員全員、管理者などの経歴を証明するもので、この書類の提出は必須となります。しかし、特に法人の場合、経歴が複数ある場合や、空白期間が存在する場合など、記載方法に戸惑うことも多いのではないでしょうか。この記事では、古物商許可申請における「略歴書」の正しい記載方法について解説します。
「略歴書」の様式の入手方法
「略歴書」の様式は、営業所の所在地を管轄する警察署で入手できます。また、各都道府県公安委員会の公式サイトからもダウンロードが可能です。ただし、記載事項が地域ごとに異なる場合があるため、提出前に都道府県ごとの規定を必ず確認してください。
「略歴書」に記載する内容
略歴書は、過去5年間の経歴を簡潔に記すもので、履歴書や職務経歴書ほど詳細な情報は求められません。経歴に空白期間がないよう注意し、無職や転職活動、フリーター期間もすべて含めて、活動内容を併せて記載するとよいでしょう。就職したばかりで5年未満の場合は、学生時代の経歴までさかのぼって記載します。
記載の最後に「以後、現在に至る」と書き足せば、略歴書が完成します。
「略歴書」の記載例と注意点
1. 無職期間がある場合
略歴書に5年間の経歴を遡って記載する際に無職の期間がある場合、その時期に何をしていたかも簡潔に記載しましょう。無職や転職活動をしていた期間は、最終学歴から記載を始めるのが一般的です。
2. 空白期間を作らない
空白期間があると申請が遅れる可能性もあるため、活動内容を記載し、空白期間を作らないようにしましょう。必要に応じて「就職活動中」「転職活動」「技術研修」など具体的に記載すると良いでしょう。
3. 記載時の「年月日」「住所」「氏名」に注意
略歴書に記載する日付は、申請日から3か月以内のものにしてください。住所は住民票通りに、氏名は記名押印または署名が必要です。シャチハタは不可となっていますので、正しい印鑑を準備しましょう。
経歴が多い場合の対応
略歴書の記載内容が多い場合、別紙を添付して対応する方法があります。経歴が長く詳細になるときは、別紙を活用し、詳細に記載しましょう。複数のページに分けて記載すると二人分の略歴書に見える恐れがあるため、別紙をまとめて添付するのが望ましいです。
なぜ5年間の経歴が必要なのか?
古物商許可の申請にあたり、一定の欠格事由に該当しないことが確認される必要があります。たとえば、罰金刑や刑事罰が確定して5年以内の場合、古物商の許可は受けられません。5年間の経歴を明らかにすることは、これらの条件に適合していることを証明するためです。
管理者の経歴も重要
古物営業法には、取り扱う物品に応じた知識や経験を管理者に持たせることが規定されています。たとえば、自動車や二輪車、宝飾品など特定の分野を取り扱う営業所の管理者には、物品の真贋を見分けるための知識が求められる場合があります。専門的な経験や知識がない場合、講習会への参加や研修など、対応策を検討することが推奨されます。
まとめ
- 「略歴書」は、提出地域の警察署または公安委員会で取得できる
- 経歴は直近5年間を空白なく記載し、住民票に基づいた正確な住所を記入する
- 管理者には、物品の特性に応じた知識や経験が求められる可能性がある
略歴書は単なる書類ではなく、許可申請において重要な役割を果たします。不明点がある場合は、専門の行政書士に相談することをおすすめします。
お問い合わせはこちらから
いかがでしたでしょうか?
事前準備をしっかりやれば、そこまで怖くないはずです。
ただどうしても時間が取れない・・・
申請書の書き方がいまいち分からない・・・
といった方は迷わず専門家にまずは相談することをお勧めします。
弊所でも古物商申請に関するご相談は受け付けております。
問合せはこちらから↓